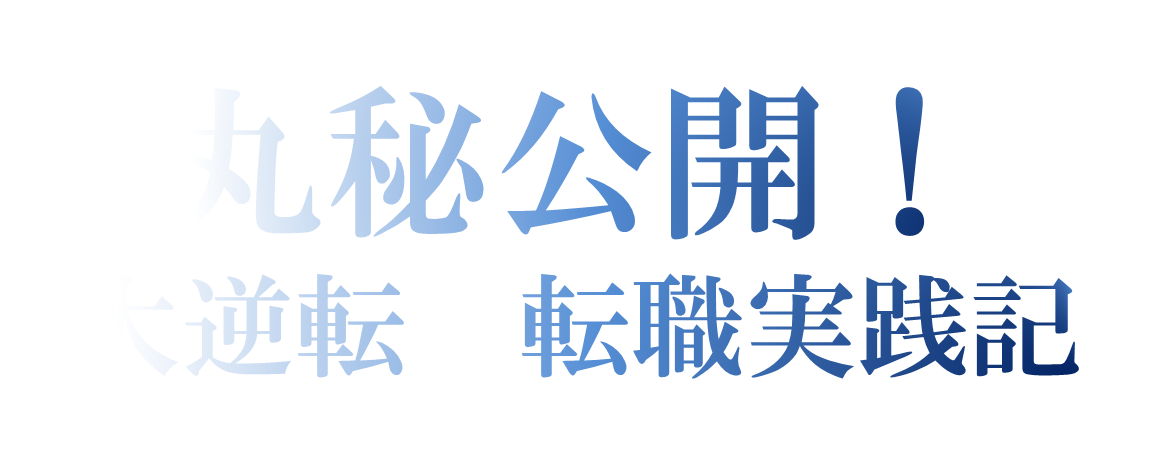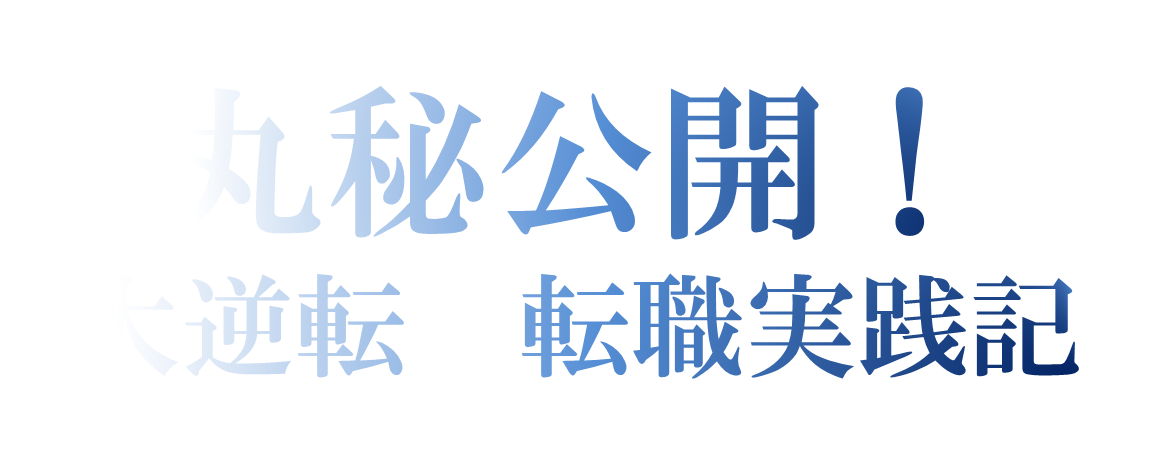
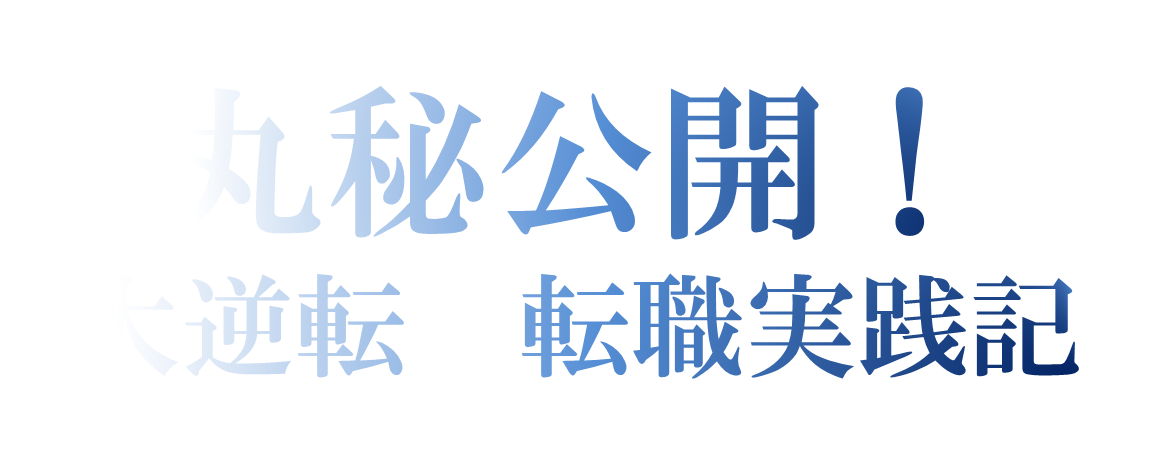
Dさんは、私が印象的な受講者として、各所で紹介している方です。
ですから、見覚えのある人もいるかもしれません。
ただ、詳しい事情を紹介するのはこれが初めてです。
私がDさんに初めて会ったのは、私が講師を務めていた自己PR文作成講座の会場でした。
(現在は実施していません)
一方的に説明するだけでなく、手順を踏んで実際に1枚の自己PR文を作り上げる、演習講座です。
受講者の中で、ただ1人一向にペンが進まず、際立って終始元気のない受講者がいました。
うつむいて「負のオーラ」を発している男性。
それが、Dさんでした。
講座でのDさんは、上述のような様子で熱意が感じられませんでした。
だからこそ、翌日個別コンサルティングを受けたいと連絡が入ったのは、少し意外でした。
後日長時間のヒアリングをして、Dさんの現状がわかりました。
Dさんが前職を退職したのは、実に2年半前。
どこに応募してもまったく面接に進めないので、この1年間は応募意欲も無くなってしまったということ。
しかし貯金も底をつきそうになったため、一縷の望みで私のコンサルティングに申し込まれたのでした。
退職から1年も経てば、「長期失業者」として評価に大きく影響します。
それが「2年半」の失業となると、致命的とも言える長さです。
しかもDさんは、すでに若いとは言えない42歳という年齢。
おまけに、Dさんは求人の少ない地方の在住でしたが、家庭の事情で職を求めて都会に単身赴任することもできません。
まさしく三重苦。
Dさんが現状を抜け出すのは並大抵のことではないと、改めて痛感しました。
実は2年半前まで、Dさんは某上場企業の経理課長を務める、優秀なサラリーマンでした。
私はそんなDさんがなぜ今まで転職できなかったのか、むしろ不思議に感じました。
口の重かったDさんが少しずつ話してくれたのは、特殊な退職事情でした。
(一部メディアではニュースにも取り上げられた程なので、詳しい事情は伏せます)
Dさんの勤務していた会社の経営幹部が、巨額な不正を働いていました。
経理部門の実質的な実務責任者であったDさんは、ある時不自然なお金の動きに気づき、独自に調査して不正の事実にたどり着きました。
事が重大なため対処に苦悩しながら、最終的にDさんは内部告発を行いました。
その会社はもともと多くの問題を抱えていた会社で、業績は不振に陥っていました。
そして、不正が明るみに出たことがきっかけとなって業績が急激に傾き、結果的に倒産するに至ったのです。
同僚は皆、沈没しそうな泥舟を飛び降りて、我先に転職していきました。
しかし、Dさんは告発の責任を感じ、そして経理責任者として、最後まで会社に残って清算業務を全うしました。
そんな厳しい試練に遭遇したDさんは、今度は家庭に問題を抱えます。
会社の倒産と失業が影響してか、奥さんが精神的に不安定になってしまったのです。
そのため、Dさんが常時付き添わなければなりませんでした。
奥さんの病状が落ち着いてDさんが目を離せるようになった頃には、退職から1年以上が過ぎていました。
つまり、転職活動を始める前に、すでにDさんは「長期失業者」の状態だったのです。
問題は、そうした事情がDさんの応募書類には一切書かれていないことでした。
応募書類に書かれていたのは、「会社都合による退職」という表現だけ。
Dさんの退職が倒産によるやむを得ない事情であることも。
退職後のブランクが奥さんの病気のためだったことも。
一切触れていないのです。
つまり、採用担当者がDさんの書類を見れば、
「会社をリストラされて、長期間転職に失敗している人」
と解釈されておかしくない状態だったのです。
Dさんはそれらを、
「公にしてはならない会社の事情」
「隠すべき恥ずかしい家庭の事情」
と考えたからです。
それでは不採用が続くのも無理はありません。
ただでさえ三重苦を患っているDさんが、そうしたやむを得ない事情を隠したまま転職に成功するのは、不可能です。
私はDさんに、むしろ積極的に事情を説明するべきだと説得しました。
そうすれば、マイナス評価が減らせるどころか、Dさんの長所を印象的にアピールすることさえできるからです。
「不正に気づく会計能力」
「不正を見逃せない正義感」
「清算業務を全うする責任感」
「家族に寄り添う思いやり」…
Dさんは当初は頑なに同意しませんでしたが、最後には私のアドバイスを受け入れてくれました。
履歴書・職務経歴書をブラッシュアップしたら、最後の仕上げです。
「自己PR文に、倒産のエピソードを詳しく書きましょう」
まとまった文章で表現できる自己PR文こそ、Dさんの仕事ぶりを魅力的に伝える格好の場所です。
Dさんは当初、「すばやく正確に経理業務をこなします」のような、「無難な」自己PR文を書こうとしていました。
しかし私は、
「毒にも薬にもならないような自己PR文なら、書いても意味がないですよ」
と押し切りました。
Dさんは、不正を告発するような従業員は嫌がられるのではと懸念しました。
しかし私は、その人間性を高く評価する経営者は必ずいると思ったのです。
書類の内容については、幾度も意見を戦わせました。
そして、最終的にはライバル応募者とは一線を画すであろう、非常に印象的で読み応えのある応募書類が完成しました。
それだけではありません。
Dさんは、応募活動に落選し続けて強い自己否定に陥っていました。
しかし、Dさん自身が自分の強み・特長を明確にする作業を通じて、次第に自信を取り戻していったのです。
2年半のハンディキャップを克服するのは並大抵のことではありませんが、私は「奇跡」が起こるのではないかと感じました。
果たして…
応募再開から3週間後、Dさんは新たな苦悩を味わっていました。
それは、「複数の内定企業から入社先を選ぶ苦悩」でした。
Dさんを非常に高く評価する企業が続出し、トントン拍子で内定が続いたのです。
最終的にDさんは、自宅からは少し遠く、高速道路で通勤が必要な企業を選びました。
将来の幹部候補と評価され、しかも前職の年収を上回る条件で、課長として採用されたからです。
Dさんは、この企業から内定を得た時、なぜ自分を選んだのか役員に聞いたそうです。
無理もありません。
その求人募集には数十人の応募があり、他にDさんより条件の良い人はたくさんいたはずだからです。
するとその役員は、
「会社倒産のあの自己PR文を読んで、『この人を採りたい』と思ったんですよ」
と言ったそうです。
Dさんはすっかり自信を取り戻し、自分を心から必要とされる場で生き生きと働いています。
私にとっても、勇気を出して伝えることの大切さを改めて痛感したサポート経験でした。